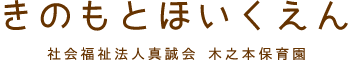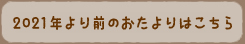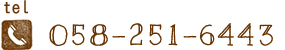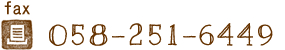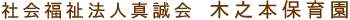おたより紹介
トップページ > おたより紹介
きのもと 10月号
令和7年10月1日 木之本保育園
9月も後半になってようやく秋の空気に入れ替わり、日中はそれなりに暑くても、朝夕はずいぶん涼しさも感じられるようになってきました。
残暑が厳しかった間は、運動会練習を室内で少しずつおこなってきましたが、9月下旬からは涼しい日も続き、ようやく戸外で伸び伸びと運動会の練習をできるようになりました。子ども達の元気な声が園庭に響いています。
運動会当日、子ども達は練習の成果をおもいきり発揮することと思いますのでご期待ください。
そして、運動会が終わっても秋の青空のもと、元気いっぱいに体を使う遊びを楽しませてあげたいと思っています。
10月のねらい
- 戸外で友達と一緒に、跳ぶ・走る・歩くなどの運動を楽しむ。
- 秋の自然に触れて、季節の変化に興味や関心をもつ。
- 約束や決まりを守って遊び、あと片付けは、みんなで力を合わせてしようとする。
10月の行事予定
| 日付 | 行事内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3日(金) |
|
|||
| 4日(土) |
|
|||
| 5日(日) |
|
|||
| 6日(月) |
|
|||
| 7日(火) |
|
|||
|
||||
| 9日(木) |
|
|||
| 12日(日) |
|
|||
| 13日(月) |
|
|||
| 15日(水) |
|
|||
| 16日(木) |
|
|||
| 17日(金) |
|
|||
| 18日(土) |
|
|||
| 20日(月)~23日(木) |
|
|||
| 23日(木) |
|
|||
| 27日(月) |
|
木之本地区市民運動会への出演について
10月12日(日)、木之本地区の市民運動会が開催され、ばら組以上の園児が出演することになっています。
集合時間等について、以下のとおり再度お知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。多数の参加をお待ちしております。
| 1.日時 | 10月12日(日) ※雨天の場合は、13日(月・祝)に延期されます。 |
|---|---|
| 2.場所 (集合場所) |
徹明さくら小学校グラウンド 入場門付近に午前10時25分に集合 |
| 3.参加園児 | すみれ・さくら・たんぽぽ・ばら組(もも組は参加しません) |
| 4.出演時間 | 午前10時45分頃 ※進行状況により多少前後する可能性があります。 演目:「わらってシャーッ!」「あおきいろ」 |
| 5.服装 | 半袖ユニフォーム上下 (寒い場合は、長袖ユニフォームでもかまいません。) ※ばら組の服装は自由とします。(動きやすい服装) |
| 6.持ち物 | ハンカチ(通園カバンはいりません) 赤白帽子は、園から持っていき、会場でかぶせます。 |
| 7.解散 | 出場後(午前11時頃)に現地解散いたします。保護者の方は、退場場所付近でお待ちください。なお、おみやげがありますので、必ず受け取ってお帰りください。 |
| 8.駐車場 | 当日、園の職員駐車場への駐車を可能とします。ただし、駐車可能台数は10台程度です。また利用予約はおこないません。他の方の迷惑にならないよう駐車いただき、市民運動会出演終了後はすみやかに移動してください。(道路への駐車はできません。) なお、市民運動会当日は、小学校駐車場や公民館駐車場には駐車できないとのことですのでご注意ください。(自転車での来場はできるとのことです。) |
秋の遠足といもほり体験について
すみれ・さくら組の10月の行事である「秋の遠足」(梅林公園)と「いもほり体験」について、同じ時期での実施であるため、両方を実施することが困難な状況です。
昨年度、山県市の体験農園にて、当時のすみれ組とさくら組がさつまいもほり体験をおこないましたが、時間が短く、収穫できるさつまいもの量も少なかったため、あまり満足できる内容ではありませんでした。また、昨今のインバウンド需要の高まりにより、貸切バスを1か月に2回予約することが難しく、昨年は、梅林公園への秋の遠足を中止にせざるをえませんでした。
そのような状況を保護者親睦会役員会にて説明し、ご相談させていただきました。その結果、今年度は、山登りをしたり公園内で午後まで遊ぶことのできる秋の遠足を実施し、いもほり体験については見送ることといたしました。
瑞穂市の畑でいもほりをおこなっていた頃は、じゃがいもほりで6月実施だったため両方実施することができていましたが、その畑が使えなくなってからは、さつまいもほりしかできるところがなく、どうしても秋の遠足の時期と重なってしまうこととなります。
申し訳ありませんが、ご理解をお願いいたします。
クラスだより
もも組「少しずつ、おはなしができるようになりました」
入園当初はほとんど言葉が出なかったり、喃語で話していた子ども達も、少しずつ自分の思いや要求等を簡単な言葉や身振りで伝えようとする姿が増え、もも組が少しにぎやかになりました。
まだ思うように話せない子は、欲しい玩具があると指差したり、「アーアー」と声を出し、保育者の手を引いて伝えようとします。保育者が動物や食べ物が出てくる絵本を見せると、2歳になった子達は、「ワンワン」と動物の名前を言ったり、保育者が絵本の食べ物を食べる仕草をすると、子ども達も「オイシー」と言って保育者の真似をしたりすることもあります。
指差しや喃語は、これからたくさんお話しができるという兆しなので、今後も子ども達一人ひとりが発する言葉を保育者が丁寧に受け止め、子ども達が話せる喜びや会話をする楽しさが感じられるようにしていきたいと思っています。
ばら組「走るのが大好きなばら組さんです」
9月から少しずつかけっこの練習をしてきました。
保育者が「かけっこしようね」と伝え、走る子の名前を順番に呼ぶと、呼ばれた子ども達は、自分からスタートの線に並んで笛の合図を聞いてうれしそうに走ります。
ゴールには保育者が待っているので、がんばって走る姿がとてもかわいらしいです。
時にはプラフォーミングに乗って歩いて渡ったり、フラフープをくぐったりして楽しんでいます。
自分の走る順番を待っている子ども達は、走っている子に「がんばれー」と大きな声で言ったり拍手をして友達の応援をする等、とても素敵な姿が見られます。
子ども達は、運動会当日、おうちの方々と一緒に参加することをとても楽しみにしています。
たんぽぽ組「ハサミがつかえるよ」
たんぽぽ組では、ハサミを使って紙を切る練習をしています。
初めてハサミを使う子は、持ち方がわからなかったり、思うように手を動かせなかったりして、ぎこちない様子でした。保育者と一緒にハサミを持ち、何度か切ることを経験すると、使い方に慣れ、少しずつ上手に使えるようになってきました。
最初は、細い紙の一回切りから始めたところ、切りやすかったようで、ほとんどの子ができるようになり、大きな紙も切れるようになりました。
だんだん慣れてくると、より細かく切ったり、丸や三角もそれらしく切ったり、広告の写真や絵を切り抜く子も増えてきました。
「先生切れたよ~」「ハサミでもっと切りたい」など、切ることが楽しくなり、とても意欲的に取り組む姿が多く見られるようになりました。そこから糊も使ってパフェ作り、ケーキやアイス作りなどにも発展しています。
ハサミを使った製作遊びをする時は毎回、子ども達が安全に楽しくハサミを使えるよう、「切ってもいいもの以外は絶対に切らないこと」「刃を人には向けないこと」など様々な使い方のルールを子ども達にその都度伝え、保育者が見守る中で遊んでいます。
さくら組「トンボのメガネ作ったよ!」
秋の製作として「トンボのメガネ」を作りました。日頃からトンボのメガネの歌をクラスでよく歌っていますが、トンボになりきって動いたり、「〇〇色メガネは、どんなお空を飛んだかな?」などみんなで話しあったりしながら、歌にちなんだ遊びをたくさんしています。そのような活動の流れからトンボの製作遊びをしましたが、いろんな遊び方をしたことで子ども達もイメージをふくらませやすく、アイデアもどんどん湧いてくるようでした。
固定観念にとらわれず自由にトンボの羽の模様を描いたり、「どんなメガネがいいかな」と友達と相談したりする姿もよく見られ、みんなで楽しく作ることができました。
完成すると、自分だけのトンボのメガネを嬉しそうに見せあい、曲に合わせて動かしながら覗いてみるなどしていました。毎日のようにこのトンボのメガネで遊ぶ子が多くみんなのお気に入りになりました。
すみれ組「運動会って楽しいね!」
先日まで行われていた世界陸上。保育者が「テレビでいろいろな国の選手が一等賞を目指して競争しているの見た?」と子ども達にたずねると、「見た!すごかった!」「かっこよかった!」「ボール投げたり、跳んだりしてた!」など、テレビで見たことを口々に話してくれました。
「運動会って世界陸上みたいで、走ったり、ジャンプしたりいろいろするんだよ。その時はみんなもかっこいい選手になるんだよ」と伝えると、「うそ~」「がんばろ~!」「ドキドキしてきた」「早く練習しようよ」と、今まで以上にやる気が出てきた子ども達。障害物競走やリレーの練習では、初めは「がんばれー」の声援をおくる子はちらほらでしたが、何回か練習を重ねたり世界陸上の話をしてからは大きな声で応援したり、転んでしまった子に「痛かった?」「大丈夫?」と気遣う姿も見られました。
練習中、他のクラスの子が見ているのに気がつくと、「みんな見てるよ。テレビと一緒みたい」「ドキドキする」と言いながらもうれしそうでした。自分のチームが負けてしまっても「次、がんばろう」と、年長児らしく自然と励まし合う姿も見られました。
運動会の練習を通して、自分だけの事だけでなく友達の事も気にかけたり、みんなと一緒に力を合わせる大切さ等々を学ぶ事ができたのではないかと思います。